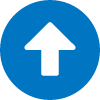Q&A集
札幌市版Q&A
下記タイトルをクリックすると、札幌市の回答が表示されます。
入院時情報連携加算算定時の日数は、どのように数えるのですか?
「入院時情報連携加算Ⅰ」は、利用者が病院又は診療所へ入院してから「3日以内」に、病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していることとあります。
この場合の「3日以内」とは、入院した当日を含まず、翌日を1日目とカウントします。(例 4月1日に入院した場合は、4月2日:1日目、4月3日:2日目、4月4日:3日目となります)
※根拠 民法第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その
期間は午前0時から始まるときは、この限りではない。(初日不算入の原則)
この場合の「3日以内」とは、入院した当日を含まず、翌日を1日目とカウントします。(例 4月1日に入院した場合は、4月2日:1日目、4月3日:2日目、4月4日:3日目となります)
※根拠 民法第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その
期間は午前0時から始まるときは、この限りではない。(初日不算入の原則)
2019年10月
医療系サービスを位置付ける場合、主治医意見書で確認するだけでは駄目なのでしょうか
運営基準では、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない(運営基準第13条十八)とされており、医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限り行うものとされています(運営基準第13条十九)。(解釈通知においても同様) したがって、居宅サービス計画に医療サービスを位置付ける場合は、主治の医師等への意見の確認は必要であり、サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、専門的な見地からの意見を求めることが望ましいと考えます。また、やむを得ない理由がある場合については、主治の医師等に対する照会等により意見を求め、照会等により主治の医師等の意見が確認できない場合は、主治医意見書での確認とすることが望ましいと考えます。主治の医師等への意見の確認方法は、運営基準上の定めはありませんが、主治医意見書については、要介護認定時に記載しているため、利用者の状態に変化があった場合など、利用者の状態像と主治医意見書記載時の利用者の状態像にかい離がある場合は、あらためて主治の医師等への確認を行っていただけるようお願いいたします。(なお、看護職員が行う居宅療養管理指導の要件などには留意願います。)
2015年9月 札幌市介護保険課
認定結果が出ず、暫定ケアプラン(A)を発行していたところ、急遽、訪問看護が必要となり、更に2度目の暫定ケアプラン(B)を発行することになりました。さて、認定結果が出た際にケアプランを作成・交付しますが、確定のケアプラン(C)は1つですか、2つ必要ですか?3つ必要ですか?
認定結果が出た際のケアプラン(C)は1つです。 この場合、認定結果が想定していた要介護度と同じであり、ニーズや目標、サービス内容等に変更のない場合は、2度目の暫定ケアプラン(B)で変わりないことをサービス担当者と本人や家族に確認しケアプラン(C)として確定します。ただし、暫定ケアプラン(B)の内容から変更がある場合は、札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第16条第3号から第11号までに掲げる一連の業務を行った上で、新しくケアプラン(C)を作成し交付する必要があります。
※暫定ケアプラン(A)及び暫定ケアプラン(B)は破棄せず、記録として残しておく必要がありますので、ご注意願います。
※暫定ケアプラン(A)及び暫定ケアプラン(B)は破棄せず、記録として残しておく必要がありますので、ご注意願います。
2015年2月 札幌市介護保険課
車椅子のレンタルがあり、冬季は返却する予定がある場合はどのような手続きが必要ですか?
福祉用具貸与を中止する場合は、居宅サービス計画の変更であるため、原則、札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例第16条第3号から第11号までに掲げる一連の業務を行う必要があります。
※「札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例」は以下札幌市のホームページからPDFファイルで確認できます。
※「札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例」は以下札幌市のホームページからPDFファイルで確認できます。
2015年2月 札幌市介護保険課
「介護保険者証」に関して、コピーをケアマネがとりますが、“デジカメ等での写真で撮影したものを事業所で印刷し「保険者証」の確認としている”というのは、認められるものなのか?
認められます。(個人情報ですので、デジカメ等の電子データへ保存する場合は、流出しないよう、取扱いにご注意下さい。)
2014年8月 札幌市介護保険課
消費税の増税でケアマネが国保連に請求する単位数にも変更があるとなっているが、居宅介護支援事業における重要事項説明書は4月に一斉に差替えが必要か? サービス事業所も同様か?
速やかに差替える必要があります。また、サービス事業所においても、同様です。
2014年4月 札幌市介護保険課
ケアプランの短期目標の期間を延長する場合の手順・対応について、教えて下さい。
1.期間を延長した場合は「経過記録」に利用者本人、家族に更新することの同意を得たことやサービス事業所へ短期目標の延長期間を伝えた旨を記載し、ケアプランに手書きで期間の修正を記載するだけで良いのか?
2.更新した場合はケアプランの差替えが必要か?差替えの際は「短期目標期間」が記載された2表のみの差替えとなるのか?
3.短期目標の期間が切れた時の対応については、法令や通知等の文章のどの部分に記載されているのか?
ケアプランを変更する際には、基準第13条第15号に基づき、原則として、基準第13条第3号から第11号までに規定されたケアプラン作成に当たっての一連の業務を行うことが必要になります。
なお、ケアプラン上の目標設定を変更する必要がなく、単に目標設定期間を延長する場合については、軽微な変更に該当する場合があるものと考えられますが、軽微な変更として行う場合には、この必要はありません。
また、ケアプランは一部を変更する都度、別葉を使用して記載する必要がありますが、サービス内容への具体的な影響がほとんど認められないような軽微な変更については、当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙に継続して記載することができます。(軽微な変更として期間を延長した場合は「経過記録」に利用者本人、家族に更新することの同意を得たことやサービス事業所へ短期目標の延長期間を伝えた旨を記載し、ケアプランに手書きで変更時点・期間の修正を記載し対応することもできます。)
なお、ケアプラン上の目標設定を変更する必要がなく、単に目標設定期間を延長する場合については、軽微な変更に該当する場合があるものと考えられますが、軽微な変更として行う場合には、この必要はありません。
また、ケアプランは一部を変更する都度、別葉を使用して記載する必要がありますが、サービス内容への具体的な影響がほとんど認められないような軽微な変更については、当該変更記録の箇所の冒頭に変更時点を明記しつつ、同一用紙に継続して記載することができます。(軽微な変更として期間を延長した場合は「経過記録」に利用者本人、家族に更新することの同意を得たことやサービス事業所へ短期目標の延長期間を伝えた旨を記載し、ケアプランに手書きで変更時点・期間の修正を記載し対応することもできます。)
2014年4月 札幌市介護保険課
通院等乗降介助は通院以外の目的で利用することは可能でしょうか?
日常生活上必要な行為かどうかを利用者の生活環境や身体状況等により判断した結果、可能な場合もあります。
利用することが可能、不可能な例をあげるとすると、以下のとおりです。
(1) 選挙 = ○
(2) 入院 = △(入院することがわかっている場合は適切ではない。)
(3) 退院 = ×
(4) ショート送迎 = ×
(5) 官公庁への届出 = 限りなく×に近い△(本人が日常生活上どうしても行かなければならないものであって、他人が代行できない場合に限り認められる。)
(6) 買物 = △(本人が日常生活上どうしても行かなければならないものであって、他人が代行できない場合に限り認められる。本人が自ら品物を選ぶ必要性がある場合等)
(7) 銀行 = 限りなく○に近い△(本人が日常生活上どうしても行かなければならないものであって、他人が代行できない場合に限り認められる。)
利用することが可能、不可能な例をあげるとすると、以下のとおりです。
(1) 選挙 = ○
(2) 入院 = △(入院することがわかっている場合は適切ではない。)
(3) 退院 = ×
(4) ショート送迎 = ×
(5) 官公庁への届出 = 限りなく×に近い△(本人が日常生活上どうしても行かなければならないものであって、他人が代行できない場合に限り認められる。)
(6) 買物 = △(本人が日常生活上どうしても行かなければならないものであって、他人が代行できない場合に限り認められる。本人が自ら品物を選ぶ必要性がある場合等)
(7) 銀行 = 限りなく○に近い△(本人が日常生活上どうしても行かなければならないものであって、他人が代行できない場合に限り認められる。)
2014年4月 札幌市介護保険課
認定結果が出ていない方も暫定のケアプランを作成した際に、サービス担当者会議を行いますが、認定結果が出ていないうちは認定の効力が発生していないので、暫定でケアプランを作成した場合、認定結果が出たらもう1回サービス担当者会議を開催しなければならないでしょうか
暫定のケアプラン作成後、認定結果が出た際もサービス担当者会議を開催する必要がありますが、認定結果が想定していた結果と同様の場合には、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができる場合があるものと考えております。
2014年1月 札幌市介護保険課
短期入所生活介護に引き続き短期入所療養介護を利用した場合、30日を超えるかどうかはどのようにカウントするのでしょうか
短期入所生活介護と短期入所療養介護は別の介護サービスであり、短期入所生活介護に引き続き短期入所療養介護を利用した場合(短期入所療養介護に引き続き短期入所生活介護を利用した場合)については、引き続き短期入所療養介護(短期入所生活介護)を利用した日が起算日となります。トータルで連続利用が30日であることをもって、連続31日目を自己負担とする取り扱いとなるものではありません。
2014年1月 札幌市介護保険課
通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の算定条件にある退院(所)日というのは、どのような入院でも該当するのでしょうか
短期集中リハビリテーションの算定要件を満たしている(短期集中リハビリテーション実施加算を算定するためには、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たす必要があり、リハビリテーションマネジメント加算を算定するためには、リハビリテーション実施計画が作成されており、その中で短期集中リハビリテーションの必要性が検討されている必要があります。)のであれば、短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件にある退院(所)日については、入院期間についての定めはありませんので、入院期間が短期間であることを持って退院(所)日が変更されないという考え方はありません。 ただし、短期集中リハビリテーションを算定するにあたって、リハビリテーション実施計画をあらためて作成する必要があるという考え方から言えば、検査入院等の本人の心身の状況に変化がないと考えられる入院については、算定条件である退院日には含まれないと考えます。
2013年11月 札幌市介護保険課
再アセスメントを行った月は、モニタリングを行わなくても減算にならないのでしょうか
運営基準では、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。(運営基準第13条十三)とされています。したがって、月1回のモニタリングを行なわなければ減算の適用を受けますが、すでに月に1回以上のモニタリングを行っていれば、再アセスメント後に、あらためてモニタリングを行わなくても、減算の適用を受けることはありません
2013年9月 札幌市介護保険課
サービス提供事業者からの依頼があれば、実績と同じようにサービス提供票を作りなおさないといけないのでしょうか
運営基準では、介護支援専門員は居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない(運営基準第13条十一)とされています。このことから、居宅サービス計画を作成した際には、利用者及び担当者に交付しなければなりませんが、利用者の希望による軽微な変更(例えばサービス提供日時の変更等で介護支援専門員が基準第13条第三号から第十一号までに掲げる一連の業務を行う必要性がないと判断したもの)を行う場合については、利用者及び担当者に交付しなければならないという記載まではされておりません。ただし、当該計画の趣旨及び内容等を各担当者と共有、連携を図ることを考えると、介護支援専門員は担当者から依頼があった際には、作り直すことが望ましいです。
2013年9月 札幌市介護保険課
短期目標期間で、終了日を設定しない場合の特別な場合について、具体的にお尋ねしたい。
利用者の状態変化が著しい場合などが考えられます。
2013年5月 札幌市保健福祉局介護保険課・事業指導担当課
目標期間の始期について
短期目標の更新やショートステイ等新たにサービスを加えて、ケアプランを変更する場合に長期目標やまだ期限が来ていない短期目標の始期もすべて「作成日(変更日)」に合わせて直さなければならないのでしょうか。
居宅サービス計画の変更に合わせて、開始時期も変更してください。 なお、軽微な変更の場合で必要箇所のみを修正し同一用紙を継続して使用する場合等については、開始時期を変更しなくても構いません。
2013年5月 札幌市保健福祉局介護保険課・事業指導担当課
ケアプランの同意欄への署名について
ケアプランの同意欄への署名について、本人が書けない場合に、記名・捺印でも良いとの事だが、ケアマネジャーの代筆は不可との事。この整合性についてお尋ねしたい。
ケアマネージャーが代筆しなければならない場合など、他の方法による場合は、その理由等を記録しておいてください。
2013年5月 札幌市保健福祉局介護保険課・事業指導担当課
他事業所へ配布する居宅サービス計画書について
他事業所へ配布する居宅サービス計画書は、同意が確認できるもののコピーでな ければならないのでしょうか。 サービス担当者会議で原案がそのまま承認された場合や多少の修正、加筆で通った場合にその場で配布させていただけると、その後のサービス提供が円滑に行えると考えます。
居宅サービス計画本書のコピーを交付するのが原則となりますが、同一内容のものであれば、各担当者との共有・連携を図った上で、サービス担当者会議の場で配布しても構いません。
2013年5月 札幌市保健福祉局介護保険課・事業指導担当課
居宅サービス計画書の同意について
運営基準に「文書による利用者の同意」を得る方法の指示はありませんが、『介護保険最新情報 Vol.38「ケアプラン点検支援マニュアルの送付について」平成20年7月18日』のP10に「利用者のサイン(印)があることを確認」とあります。文書全体の文脈から()の使い方は、「例として」「イコール」、あるいは「又は」であり、この場合は「サイン又は印」と読みました。したがって、本人が署名できない場合は、代筆を求めずとも印だけでもよいのでは、あるいは、印だけに統一してもよいのではないでしょうか。
居宅サービス計画の同意は、署名または記名・押印を原則としてください。 ただし、第6表の利用者確認欄は、押印のみでも構いません。 なお、他の方法による場合は、その理由等を記録しておいてください。
2013年5月 札幌市保健福祉局介護保険課・事業指導担当課
介護予防訪問介護における通院等乗降介助と同等のサービスの提供について
介護予防訪問介護で通院等乗降介助については、単位数がないため算定しないこととされているが、要支援者であっても通院等乗降介助の形態で介護予防訪問介護サービスを提供しなければならないような事例では、通院等乗降介助と同等のサービスのみを提供した場合であっても介護予防訪問介護を算定できる(介護予防訪問介護には通院等乗降介助が含まれている)のか。
要支援者であっても通院等乗降介助の形態で介護予防訪問介護サービスを提供しなければならないような事例では、通院等乗降介助と同等のサービスのみを提供した場合であっても介護予防訪問介護を算定できる(介護予防訪問介護には通院等乗降介助が含まれている)。
2013年2月 札幌市保健福祉局介護保険課
介護予防訪問介護の支給区分について 月に1回の通院介助のみの介護予防訪問介護が必要な者であっても、1週に1回程度の介護予防訪問介護が必要な者として、介護予防訪問介護(Ⅰ)を算定することは可能であるか。 同様に、毎週1回の介護予防訪問介護に加えて月に1回の通院介助のみの介護予防訪問介護が必要な者であっても、1週に2回程度の介護予防訪問介護が必要な者として、介護予防訪問介護(Ⅱ)を算定することが可能であるか。
介護予防訪問介護費(Ⅰ)については、週あたりの提供回数の下限が設けられていないことから、生活機能向上に係る目的を踏まえ、必要な程度の量を介護予防訪問介護計画に位置付けている場合に限り、月に1回の通院を予防訪問介護Ⅰとして算定することが可能である。同様に、毎週1回の介護予防訪問介護に加えて月に1回の通院介助が必要な者についても、1週に2回程度の介護予防訪問介護が必要な者として、介護予防訪問介護(Ⅱ)を算定することは可能である。 なお、介護予防訪問介護の算定にあたっては、月定額制であることから、利用者の負担が高額とならないように、他のインフォーマルサービスやボランティアサービスについても検討をする必要がある。
2013年2月 札幌市保健福祉局介護保険課
福祉リスクマネジメント研究所Q&A集
引用元:福祉リスクマネジメント研究所ホームページ内「事件は現場で起きている」
https://www.fukushi-risk.com/faq/index.html
https://www.fukushi-risk.com/faq/index.html
下記タイトルをクリックすると、回答が表示されます。
いつも連載を楽しみにしております。九州にあります特別養護老人ホームに勤務する生活相談員です。来年度から、ケアワーカに対して「記録について徹底するように…!!!」と法人トップから指示を受けました。確かに記録については、烏野先生も研修の中でもその重要性についてよくお話しされていたので、「とうとう来たか…」という思いです。しかし、「どうやって、何を書いていれば大丈夫なのか…?」わかりません。また、年末に併設するデイサービスで、利用者さんの誤嚥による入院があり、ご家族が「事故から一か月程度前の記録とケアプランを見せて欲しい」という訴えもありました。 このようなことから、記録について再度レクチャーを受けたいと思っているのですが…。
いつも連載を楽しみにして頂き、ありがとうございます。私としても非常に嬉しく思っています。
さて、記録について私も、「とうとう来ましたか…!!!」というのが率直なところです。 「何を記録として書けばいいのか…? どこまで記録として残さないといけないのか…? 何を書いてはいけないのか…? そして、みなさんの記録の一体どこがイケナイのか…?」について説明したいと思っています。
「なぜ、介護現場では最近とくに、『記録、記録』といわれるのでしょうか…?」 「来月に監査があるから…」、「神経質な上司がいるから…」という理由ではありません。記録を書くということは、介護業務に携わる皆さんが、利用者さんとの約束を正確に守ったことを証拠として残すという意味があります。
もちろん、記録を書く、残すという行為は、利用者さんの生活やニーズを知り、他の機関との連携を図り、介護サービスの連続性や個別性を担保するという役割は確かにあります。
ですが、リスクマネジメントという視点からみた場合の「記録」には、介護スタッフの業務が正当なものであったというスタッフ個人を守るという発想が欠かせません。スタッフが守られれば、法人も守られ、その結果として高齢者へのより質の高いサービスが保証できる、というのが私の考えです。
では、何を記録しなければいけないのでしょうか? それは、利用者さんに対して何を約束したのか? に尽きます。皆さんの約束は、ケアプランで計画された「長期目標・短期目標」そして「実施するサービス内容」に根拠があります。つまり、ケアプランで言えば別表の第2表にあたる項目ですね。この目標や、目標を達成するための具体的なサービスを、直接的な業務として遂行するのが皆さんのお仕事になるわけです。ということは、ケアプランで約束された目標や、その目標を達成させるための具体的な業務(介護)を行い、それを記録として残してはじめて、利用者さんとの「約束を守った」ということになります。
介護事故を含めた危機管理を専門としている私の立場からいえば、法人側が利用者さんやご家族から事故等で訴えられた場合、ほとんどのケースで負けてしまう結果となるのは、ケアプランで約束をした介護の内容を、正確に記録化されていないことで「やっていなかった」と判断されてしまう場合がほとんどだからです。 介護現場で働く皆さんは、実際には非常に真面目に、そして熱心に日々の業務を行っているといえます。
では、なぜ、「やっていない」という判断を下されるのでしょうか? それには理由として二つのことがあげられます。
ひとつは、ケアプランで約束をした目標や、その目標を達成するための具体的なサービス内容が、非常に抽象的な表現で設定されていることからくる曖昧さです。
介護事故で最も多い訴えは、「転倒や転落」そして「誤嚥」についてのトラブルです。ほとんどの高齢者に当てはまると思われる「転倒・転落」や「誤嚥」の予測について、実施するサービス内容として確定される表現に、「歩行中や移動時はしっかりと見守る」や、「安全な食事の提供のために見守る」といった文言が頻繁に使われています。
しかし、この「見守り」が業務としてどの程度の介助が必要で、どんな行為をもってすれば見守ったといえるのか、についての認識や判断が非常に曖昧なため、「見守り」のための業務を正確に遂行したのかどうか、そしてそれを記録化することにも難しさと戸惑いを覚えてしまうといった点です。
二つ目には、たとえ正確な業務を約束にもとづいて実行したとしても、記録として残されていないと、契約の相手方である高齢者の方に、「やったか、やっていなかったか」を確認することができないという点です。 介護サービスを利用する高齢者のほとんどが、認知症や寝たきりなどで判断能力が著しく低下もしくは減退している人ですから、確認のために過去の業務のことを尋ねても意味がない事は明らかですよね。
つまり、介護スタッフである皆さんは、契約の相手方に皆さんの業務の履行を確認できない人との間で約束をしているものですから、皆さん自身にすべての証明責任があるということになるわけです。
この証明が「記録」なんです。 最近の誤嚥をめぐる介護事故の裁判事例から記録についてのポイントを見ていきましょう。
これは、介護保険施設において、入所中のパーキンソン病患者が食事として提供された刺身を食し嚥下障害により死亡した事故に対し、老人保健施設を運営している法人に介護保険義務違反があるとして、損害賠償責任が認められた裁判です(水戸地裁平成23年6月16日判決 一部認定・一部棄却[控訴])。
今回の裁判事例では、過去の介護事故裁判で例を見ないほど、介護業務と記録についての詳細な分析を弁護人や裁判所が行っている点に注目してください。アセスメントやケアプラン、そしてサービス担当者会議での議事録から、業務としてどのような介護サービスを提供する必要があり、その必要に対してどのような目標を立て、専門家集団が何に基づいて、その目標を達成するための具体的な介護サービスを提供したのか、またその提供された介護サービスが妥当であったのか、を問うたものだったからです。
亡くなったのは大正7年4月24日生まれの事故当時86歳の男性であり、既往歴にパーキンソン症候群で、長谷川式認知症の結果もかなり悪い高齢者でした。平成16年11月3日に昼食として提供された刺身を誤嚥して窒息し心肺停止状態となり、平成17年3月17日心不全により亡くなられたケースです。
主な争点としては、刺身を常食で提供したことについての過失をめぐってです。 以下、介護提供までのプロセスとその決定過程について、説明したいと思います。
平成15年7月10日に要介護3と認定を受けた高齢者は、平成15年8月25日に老人保健施設と介護契約を締結しますが、入所前の利用者ならび家族との打ち合わせでも、男性が食事時にむせることがあるとの指摘を家族が行い、食事について家族は全粥きざみ食の提供を希望したことが、平成15年8月18日づけの医師の書面に残されていました。 結論的には、施設入所から事故発生まで、つまり平成15年9月12日から平成16年9月14日までの一年間にケアプランの見直しを合計5回行っていますが、常食での提供をしながらも、施設サービス計画書にはいずれも「男性について誤嚥機能の低下が見られる。嚥下障害があり食事や水分摂取に時にムセが見られる」など、誤嚥の危険性が高い旨またはそれと同視できるような記載が継続的にありました。 これに対して裁判所の判断は、とくに刺身を常食で提供したことの過失について、まぐろは筋がある場合には咀嚼しづらく噛み切れないこともあるため、嚥下能力が劣る高齢の入所者に提供するのに適した食物とはいい難く、介護職員は利用者の嚥下機能の低下、誤嚥の危険性に照らせば、利用者に対しそのような刺身を提供すれば、誤嚥する危険性が高いことを十分予測し得たと認められる、と判断しました。
また利用者が合計35回争点となった四品(寿司、刺身、うな重、ねぎとろ)を常食で摂取したという事実はあるものの、それは単なる結果論に過ぎないとしたうえで、利用者自身の強い希望があったとしても、安易に本件四品目を常食で提供するとの決定をすべきではなかったとも、裁判所は付け加えています。 そして常食での摂取も可能な場合(時期)も若干あったにもかかわらず、施設サービス計画書の「サービス内容」に「誤嚥に注意した見守り」とのプランを立てたことは、実際の利用者の状態とは異なるものの「職員の注意を喚起するための記載」と施設側は主張しましたが、「…注意喚起のためとはいえ、およそ存在しない症状を記載するとは考えられず、利用者には少なくとも職員の注意喚起が必要な程度には嚥下機能の低下や誤嚥の危険性があったものと認められる」として裁判所は施設側の主張を退けました。
この裁判では、5回のケアプランの見直し、「長期・短期目標」の設定、「サービス内容」を前後のサービス担当者会議の議事録まで引っ張り出して、ケアの妥当性と記録との整合性を明らかにした事例でした。
いかがでしょうか? 「長期・短期目標」や「実施するサービス内容」と、実施する介護行為そして記録の関連性が理解できたかと思われます。
つまり、「何を書くのか、どこまで書くのか、今の記録の何がイケナイのか」が分かっていただけましたでしょうか? 最後に、「監査では、記録について何も言われなかったので、自信をもっています」と豪語される法人トップもいらっしゃいますが、それはリスクマネジメントという視点からみると不十分です。
なぜなら、監査で求められる記録と、「いくらお金を取るか」という損害賠償で耐えられる記録とは、視点が全く違うということを覚えておいてください。
さて、記録について私も、「とうとう来ましたか…!!!」というのが率直なところです。 「何を記録として書けばいいのか…? どこまで記録として残さないといけないのか…? 何を書いてはいけないのか…? そして、みなさんの記録の一体どこがイケナイのか…?」について説明したいと思っています。
「なぜ、介護現場では最近とくに、『記録、記録』といわれるのでしょうか…?」 「来月に監査があるから…」、「神経質な上司がいるから…」という理由ではありません。記録を書くということは、介護業務に携わる皆さんが、利用者さんとの約束を正確に守ったことを証拠として残すという意味があります。
もちろん、記録を書く、残すという行為は、利用者さんの生活やニーズを知り、他の機関との連携を図り、介護サービスの連続性や個別性を担保するという役割は確かにあります。
ですが、リスクマネジメントという視点からみた場合の「記録」には、介護スタッフの業務が正当なものであったというスタッフ個人を守るという発想が欠かせません。スタッフが守られれば、法人も守られ、その結果として高齢者へのより質の高いサービスが保証できる、というのが私の考えです。
では、何を記録しなければいけないのでしょうか? それは、利用者さんに対して何を約束したのか? に尽きます。皆さんの約束は、ケアプランで計画された「長期目標・短期目標」そして「実施するサービス内容」に根拠があります。つまり、ケアプランで言えば別表の第2表にあたる項目ですね。この目標や、目標を達成するための具体的なサービスを、直接的な業務として遂行するのが皆さんのお仕事になるわけです。ということは、ケアプランで約束された目標や、その目標を達成させるための具体的な業務(介護)を行い、それを記録として残してはじめて、利用者さんとの「約束を守った」ということになります。
介護事故を含めた危機管理を専門としている私の立場からいえば、法人側が利用者さんやご家族から事故等で訴えられた場合、ほとんどのケースで負けてしまう結果となるのは、ケアプランで約束をした介護の内容を、正確に記録化されていないことで「やっていなかった」と判断されてしまう場合がほとんどだからです。 介護現場で働く皆さんは、実際には非常に真面目に、そして熱心に日々の業務を行っているといえます。
では、なぜ、「やっていない」という判断を下されるのでしょうか? それには理由として二つのことがあげられます。
ひとつは、ケアプランで約束をした目標や、その目標を達成するための具体的なサービス内容が、非常に抽象的な表現で設定されていることからくる曖昧さです。
介護事故で最も多い訴えは、「転倒や転落」そして「誤嚥」についてのトラブルです。ほとんどの高齢者に当てはまると思われる「転倒・転落」や「誤嚥」の予測について、実施するサービス内容として確定される表現に、「歩行中や移動時はしっかりと見守る」や、「安全な食事の提供のために見守る」といった文言が頻繁に使われています。
しかし、この「見守り」が業務としてどの程度の介助が必要で、どんな行為をもってすれば見守ったといえるのか、についての認識や判断が非常に曖昧なため、「見守り」のための業務を正確に遂行したのかどうか、そしてそれを記録化することにも難しさと戸惑いを覚えてしまうといった点です。
二つ目には、たとえ正確な業務を約束にもとづいて実行したとしても、記録として残されていないと、契約の相手方である高齢者の方に、「やったか、やっていなかったか」を確認することができないという点です。 介護サービスを利用する高齢者のほとんどが、認知症や寝たきりなどで判断能力が著しく低下もしくは減退している人ですから、確認のために過去の業務のことを尋ねても意味がない事は明らかですよね。
つまり、介護スタッフである皆さんは、契約の相手方に皆さんの業務の履行を確認できない人との間で約束をしているものですから、皆さん自身にすべての証明責任があるということになるわけです。
この証明が「記録」なんです。 最近の誤嚥をめぐる介護事故の裁判事例から記録についてのポイントを見ていきましょう。
これは、介護保険施設において、入所中のパーキンソン病患者が食事として提供された刺身を食し嚥下障害により死亡した事故に対し、老人保健施設を運営している法人に介護保険義務違反があるとして、損害賠償責任が認められた裁判です(水戸地裁平成23年6月16日判決 一部認定・一部棄却[控訴])。
今回の裁判事例では、過去の介護事故裁判で例を見ないほど、介護業務と記録についての詳細な分析を弁護人や裁判所が行っている点に注目してください。アセスメントやケアプラン、そしてサービス担当者会議での議事録から、業務としてどのような介護サービスを提供する必要があり、その必要に対してどのような目標を立て、専門家集団が何に基づいて、その目標を達成するための具体的な介護サービスを提供したのか、またその提供された介護サービスが妥当であったのか、を問うたものだったからです。
亡くなったのは大正7年4月24日生まれの事故当時86歳の男性であり、既往歴にパーキンソン症候群で、長谷川式認知症の結果もかなり悪い高齢者でした。平成16年11月3日に昼食として提供された刺身を誤嚥して窒息し心肺停止状態となり、平成17年3月17日心不全により亡くなられたケースです。
主な争点としては、刺身を常食で提供したことについての過失をめぐってです。 以下、介護提供までのプロセスとその決定過程について、説明したいと思います。
平成15年7月10日に要介護3と認定を受けた高齢者は、平成15年8月25日に老人保健施設と介護契約を締結しますが、入所前の利用者ならび家族との打ち合わせでも、男性が食事時にむせることがあるとの指摘を家族が行い、食事について家族は全粥きざみ食の提供を希望したことが、平成15年8月18日づけの医師の書面に残されていました。 結論的には、施設入所から事故発生まで、つまり平成15年9月12日から平成16年9月14日までの一年間にケアプランの見直しを合計5回行っていますが、常食での提供をしながらも、施設サービス計画書にはいずれも「男性について誤嚥機能の低下が見られる。嚥下障害があり食事や水分摂取に時にムセが見られる」など、誤嚥の危険性が高い旨またはそれと同視できるような記載が継続的にありました。 これに対して裁判所の判断は、とくに刺身を常食で提供したことの過失について、まぐろは筋がある場合には咀嚼しづらく噛み切れないこともあるため、嚥下能力が劣る高齢の入所者に提供するのに適した食物とはいい難く、介護職員は利用者の嚥下機能の低下、誤嚥の危険性に照らせば、利用者に対しそのような刺身を提供すれば、誤嚥する危険性が高いことを十分予測し得たと認められる、と判断しました。
また利用者が合計35回争点となった四品(寿司、刺身、うな重、ねぎとろ)を常食で摂取したという事実はあるものの、それは単なる結果論に過ぎないとしたうえで、利用者自身の強い希望があったとしても、安易に本件四品目を常食で提供するとの決定をすべきではなかったとも、裁判所は付け加えています。 そして常食での摂取も可能な場合(時期)も若干あったにもかかわらず、施設サービス計画書の「サービス内容」に「誤嚥に注意した見守り」とのプランを立てたことは、実際の利用者の状態とは異なるものの「職員の注意を喚起するための記載」と施設側は主張しましたが、「…注意喚起のためとはいえ、およそ存在しない症状を記載するとは考えられず、利用者には少なくとも職員の注意喚起が必要な程度には嚥下機能の低下や誤嚥の危険性があったものと認められる」として裁判所は施設側の主張を退けました。
この裁判では、5回のケアプランの見直し、「長期・短期目標」の設定、「サービス内容」を前後のサービス担当者会議の議事録まで引っ張り出して、ケアの妥当性と記録との整合性を明らかにした事例でした。
いかがでしょうか? 「長期・短期目標」や「実施するサービス内容」と、実施する介護行為そして記録の関連性が理解できたかと思われます。
つまり、「何を書くのか、どこまで書くのか、今の記録の何がイケナイのか」が分かっていただけましたでしょうか? 最後に、「監査では、記録について何も言われなかったので、自信をもっています」と豪語される法人トップもいらっしゃいますが、それはリスクマネジメントという視点からみると不十分です。
なぜなら、監査で求められる記録と、「いくらお金を取るか」という損害賠償で耐えられる記録とは、視点が全く違うということを覚えておいてください。
2005年1月 福祉リスクマネジメント研究所 所長 烏野 猛
先生に質問ですが、高齢者施設内での転倒・転落や誤嚥の事故で、実際に裁判で勝ったケースはあるのでしょうか?先生のお話では、施設内で事故が起こった場合、記録の不備や職員の未熟さから、圧倒的に利用者や家族側に有利な条件(法人側には不利)ばかりがあるように思います。 実際に裁判にまで到ったケースで施設側が勝ったような事例から、何に注意をして部下を指導し、事故が起こらない仕組みをどう作ればいいのか、といつも悩んでいます。
そうですね。皆さんの業務の中身をみると、躓いて転べば大腿骨の頸部骨折につながり、食事をすれば誤嚥による窒息死に到るような方ばかりをお世話しているわけですから、対照的に保育所や幼稚園での子どもに同じような状況が発生したとしても、大けがやまた亡くなるようなことはなく、注意義務のかけかたや過失のとらえ方も随分と違うものがありますよね。
介護事故をめぐる多くの家族(遺族)の主張を聞いても、「そもそも高齢者が転んだら、こうなることは…」「そもそもお年寄りの食事中に少しでも目を離すなんて…」という圧倒的に「ごもっとも」な主張で向かってくるわけです。心の中では、「なら、家族で見てても同じようなことが起こりますよ…」と言いたいところですが、そうとも言えず、「私たちはお金も払ってて、あなたたちは介護のプロなんでしょ…!!!」とくるものですから、もう何も反論できなくなるわけです。
あげくの果てには、「おじいちゃんを返して…!!!あんなにも好きだったのに…。この人殺し…」とくれば、もう話し合いでは解決せず、裁判になってしまうわけですよね。
法人側にとっても、変に和解や示談でことを済ませるより、裁判でスタッフの介護行為の正当性を主張し、職員や組織を守る展開が、今後の法人づくりの上でも良い場合もあります。
介護事故が裁判にまで発展したケースでいえば、ご質問の通り、法人が負けてしまうケースがほとんどです。
下記に、最近の高齢者施設での誤嚥事故で法人側が勝ったケースを紹介しますが、裁判の勝ち負けは担当した弁護士が介護現場の実態や介護事故が医療事故と微妙に異なることが分かっているのか、といった専門家としての力量にも左右されますし、また両方の意見を聞く裁判官の得手不得手にも左右されるのが事実です。 逆に裁判で勝ちを収めた事例から、「こういう点を主張すれば、はたして勝てたのか…?」という疑問をぶつけながら質問にお答えしたいと思います。
当時82歳の女性が、高齢者施設に入所し3か月目の夕食時に誤嚥、死亡した事件ですが、利用者である高齢女性の死因と施設及び介護スタッフらの過失が争点になったものです(平成22年8月26日横浜地裁棄却<確定>)。
この事例では、遺族である高齢女性の夫と彼らの長男長女が原告として登場し、また誤嚥直後の様子を同じ入所者である認知症の利用者の証言が出されるなどした事件でした。 争点の一つである死因については、夕食時に食事を詰まらせたことによる誤嚥なのか、それとも利用者の持病であった心筋梗塞または脳梗塞によって意識がなくなり、それに伴って吐き戻しの誤嚥を原因とするものなのかが問われました。 判決では結論として食物の誤嚥ではなく、既往症から考えて脳梗塞もしくは心筋梗塞による発作からの吐き戻しによる窒息死と判断しています。
しかし、判決文をみると、施設に入所中、心疾患および脳疾患に関する投薬はなく、また脳梗塞や心筋梗塞の発症を抑制するための対応もとられていないこと、さらに裁判所は食事による誤嚥ではないことの理由として、「…仮に食物を誤嚥し、窒息して意識消失に至ったのであれば、当人は苦しんだり、むせ込んだり、胸を叩いたりするなどの動作をしたり、音を立てたりするのが自然な成り行きと考えられるところ、当人にこのような動作をしたことを認めるに足る証拠はない…」という判断をしています。
しかし誤嚥というのは、むせない誤嚥も実際の介護事故では多く、過去にもむせない誤嚥を経験したことがないヘルパーが誤嚥であることを気づかずに救急対応が遅れ裁判になったケースも存在します。
このようなことから、死因についてはかなりの疑問が残るところです。
二つ目の争点である施設ならび介護スタッフの過失については、誤嚥等の緊急時における職員教育、食事介助中の介助者の立ち位置、見守りを含めた観察、誤嚥後の救命措置の方法などが細かく問われました。 ここでも判決では、施設ないし介護スタッフの働き方からみた過失について、「職員教育」では救急救命マニュアルの作成、急変時にとるべき内容及び方法、医師及び看護師への連絡、コールの手順、救急搬送の手順書が存在し、年一回の定期的な勉強会の実施等から、スタッフ教育が不十分であるとまでは評価できない、という認識をしました。
ですが、これらの手順書やマニュアルがいつ頃つくられたもので、事故当時でも有効なものであるのか、また研修の内容、頻度、到達度等、効果測定なるものがあるのか、といった研修や教育の有効性が問われるべきだったと思います。つまり年一回の勉強会で足りる知識・技能であったものなのか、参加者は全員なのか、という視点です。
また、「適切な人員配置」についても、裁判所が言う通り、事故当時の当施設において基準省令上の人員基準は満たしており、この部分では問題はないように思われます。
しかし、人員の基準ではなく、たとえ利用者との割合で人員基準は満たしていた場合でも、「ヒヤリハッと報告書」などから、時間帯また繁忙時間における職員配置に無理がなかったのか、報告書からも職員配置が手薄な場面での事故が頻発していたのではないか、といった視点が今後の争点となってもおかしくはないと思います。
次に「入所者を適切な位置で食事をさせ、注意深く観察することの義務」についても、介護士が突然の意識消失を予見することができず、観察の程度も不十分ではなく、席替えをしなかった点について過失はない、と裁判所は判断しました。
しかし利用者のアセスメントから、脳梗塞や心筋梗塞などの持病は把握できるはずですし、また事故がおきた一週間程度前から5回の嘔吐の事実を認識していながら、見守り等も含めた食事中の誤嚥を予見できなかったとはいえないように思います。
最後に、介護施設における裁判事例もかなりの数にのぼり、過失責任を問う上でも争点の項目が多様化しているように思います。
たとえば、「AEDの設置義務」や「適切な救命措置をとらなかった過失」についても争点になりましたが、高齢者施設にAEDの設置義務がないこと、またエアウェイ挿入や吸引の行為は法令上禁止されている医行為に該当する可能性が極めて高いため使用しなかったことに対しての違法性はないと判断されています。さらに、アンビューバッグの使用や、心臓マッサージの実施、痰切り用(吸引器用)カテーテルの使用や掃除機用カテーテルの使用といった細かい項目についても、今後、誤嚥事故等での介護職員・法人に求められる緊急時の対応方法に示唆するものがあると思われます。
ただ、ご質問にあるように、「何に注意をして部下を指導し、事故が起こらない仕組みをどう作ればいいのか」については、「ヒヤリ・ハッと報告書」や「事故報告書」を手かがりに、細かな検証作業が必要です。
具体的には、「記録の整合性」です。 つまり、アセスメントからケアプランへの落とし込み、そして長期・短期目標を記載した介護計画から実際に提供された介護記録への落とし込みへの振り返りを行うことで、「記録として何を書く必要があり、どんな文言が不要なのか」といった考察が、必要とされる情報収集の項目を明らかにし、同じ事故を繰り返さない要素になりますから。 具体的な例をあげると、「転倒に注意しながら安定した歩行」とケアプラン上に長期・短期目標としてあげながら、歩行・補助具の活用等の記録がまったくなく、転倒に配慮した記録が一切なかったり、またケアプランの長期・短期目標に「違和感なく食べるものの、今後、咀嚼しやすい献立」としながら、実際の実施記録には「食事の際のむせ込みが多く続く」というような、逆のことが記録化されているなど、矛盾する整合性のない記載がある記録を多く目にします。
言い換えると、転倒や誤嚥については、長期・短期目標にそれらの注意事項があげられていながら、実施記録の方では些細な表現のなかにプランや目標とまったく逆のことが記載されたような記録が目につくということです。「記録を読んで、どんなケアプランなのかが想像できるか?」、「ケアプランをみて、どんなアセスメントなのかが想像できるか?つまり、利用者像がイメージできるか?」といった逆の視点から、「限られた時間や交渉のなかで何を聞いておかなければいけないのか」「何をケアプラン上の目標としてあげるべきなのか」。そして「実際の介護サービスを提供していくうえで、現実可能なものであるのか」という視点を養っておくことで、裁判の勝敗はともかくとして、介護スタッフが実践している行為の正当性が裏づけられますから。
介護事故をめぐる多くの家族(遺族)の主張を聞いても、「そもそも高齢者が転んだら、こうなることは…」「そもそもお年寄りの食事中に少しでも目を離すなんて…」という圧倒的に「ごもっとも」な主張で向かってくるわけです。心の中では、「なら、家族で見てても同じようなことが起こりますよ…」と言いたいところですが、そうとも言えず、「私たちはお金も払ってて、あなたたちは介護のプロなんでしょ…!!!」とくるものですから、もう何も反論できなくなるわけです。
あげくの果てには、「おじいちゃんを返して…!!!あんなにも好きだったのに…。この人殺し…」とくれば、もう話し合いでは解決せず、裁判になってしまうわけですよね。
法人側にとっても、変に和解や示談でことを済ませるより、裁判でスタッフの介護行為の正当性を主張し、職員や組織を守る展開が、今後の法人づくりの上でも良い場合もあります。
介護事故が裁判にまで発展したケースでいえば、ご質問の通り、法人が負けてしまうケースがほとんどです。
下記に、最近の高齢者施設での誤嚥事故で法人側が勝ったケースを紹介しますが、裁判の勝ち負けは担当した弁護士が介護現場の実態や介護事故が医療事故と微妙に異なることが分かっているのか、といった専門家としての力量にも左右されますし、また両方の意見を聞く裁判官の得手不得手にも左右されるのが事実です。 逆に裁判で勝ちを収めた事例から、「こういう点を主張すれば、はたして勝てたのか…?」という疑問をぶつけながら質問にお答えしたいと思います。
当時82歳の女性が、高齢者施設に入所し3か月目の夕食時に誤嚥、死亡した事件ですが、利用者である高齢女性の死因と施設及び介護スタッフらの過失が争点になったものです(平成22年8月26日横浜地裁棄却<確定>)。
この事例では、遺族である高齢女性の夫と彼らの長男長女が原告として登場し、また誤嚥直後の様子を同じ入所者である認知症の利用者の証言が出されるなどした事件でした。 争点の一つである死因については、夕食時に食事を詰まらせたことによる誤嚥なのか、それとも利用者の持病であった心筋梗塞または脳梗塞によって意識がなくなり、それに伴って吐き戻しの誤嚥を原因とするものなのかが問われました。 判決では結論として食物の誤嚥ではなく、既往症から考えて脳梗塞もしくは心筋梗塞による発作からの吐き戻しによる窒息死と判断しています。
しかし、判決文をみると、施設に入所中、心疾患および脳疾患に関する投薬はなく、また脳梗塞や心筋梗塞の発症を抑制するための対応もとられていないこと、さらに裁判所は食事による誤嚥ではないことの理由として、「…仮に食物を誤嚥し、窒息して意識消失に至ったのであれば、当人は苦しんだり、むせ込んだり、胸を叩いたりするなどの動作をしたり、音を立てたりするのが自然な成り行きと考えられるところ、当人にこのような動作をしたことを認めるに足る証拠はない…」という判断をしています。
しかし誤嚥というのは、むせない誤嚥も実際の介護事故では多く、過去にもむせない誤嚥を経験したことがないヘルパーが誤嚥であることを気づかずに救急対応が遅れ裁判になったケースも存在します。
このようなことから、死因についてはかなりの疑問が残るところです。
二つ目の争点である施設ならび介護スタッフの過失については、誤嚥等の緊急時における職員教育、食事介助中の介助者の立ち位置、見守りを含めた観察、誤嚥後の救命措置の方法などが細かく問われました。 ここでも判決では、施設ないし介護スタッフの働き方からみた過失について、「職員教育」では救急救命マニュアルの作成、急変時にとるべき内容及び方法、医師及び看護師への連絡、コールの手順、救急搬送の手順書が存在し、年一回の定期的な勉強会の実施等から、スタッフ教育が不十分であるとまでは評価できない、という認識をしました。
ですが、これらの手順書やマニュアルがいつ頃つくられたもので、事故当時でも有効なものであるのか、また研修の内容、頻度、到達度等、効果測定なるものがあるのか、といった研修や教育の有効性が問われるべきだったと思います。つまり年一回の勉強会で足りる知識・技能であったものなのか、参加者は全員なのか、という視点です。
また、「適切な人員配置」についても、裁判所が言う通り、事故当時の当施設において基準省令上の人員基準は満たしており、この部分では問題はないように思われます。
しかし、人員の基準ではなく、たとえ利用者との割合で人員基準は満たしていた場合でも、「ヒヤリハッと報告書」などから、時間帯また繁忙時間における職員配置に無理がなかったのか、報告書からも職員配置が手薄な場面での事故が頻発していたのではないか、といった視点が今後の争点となってもおかしくはないと思います。
次に「入所者を適切な位置で食事をさせ、注意深く観察することの義務」についても、介護士が突然の意識消失を予見することができず、観察の程度も不十分ではなく、席替えをしなかった点について過失はない、と裁判所は判断しました。
しかし利用者のアセスメントから、脳梗塞や心筋梗塞などの持病は把握できるはずですし、また事故がおきた一週間程度前から5回の嘔吐の事実を認識していながら、見守り等も含めた食事中の誤嚥を予見できなかったとはいえないように思います。
最後に、介護施設における裁判事例もかなりの数にのぼり、過失責任を問う上でも争点の項目が多様化しているように思います。
たとえば、「AEDの設置義務」や「適切な救命措置をとらなかった過失」についても争点になりましたが、高齢者施設にAEDの設置義務がないこと、またエアウェイ挿入や吸引の行為は法令上禁止されている医行為に該当する可能性が極めて高いため使用しなかったことに対しての違法性はないと判断されています。さらに、アンビューバッグの使用や、心臓マッサージの実施、痰切り用(吸引器用)カテーテルの使用や掃除機用カテーテルの使用といった細かい項目についても、今後、誤嚥事故等での介護職員・法人に求められる緊急時の対応方法に示唆するものがあると思われます。
ただ、ご質問にあるように、「何に注意をして部下を指導し、事故が起こらない仕組みをどう作ればいいのか」については、「ヒヤリ・ハッと報告書」や「事故報告書」を手かがりに、細かな検証作業が必要です。
具体的には、「記録の整合性」です。 つまり、アセスメントからケアプランへの落とし込み、そして長期・短期目標を記載した介護計画から実際に提供された介護記録への落とし込みへの振り返りを行うことで、「記録として何を書く必要があり、どんな文言が不要なのか」といった考察が、必要とされる情報収集の項目を明らかにし、同じ事故を繰り返さない要素になりますから。 具体的な例をあげると、「転倒に注意しながら安定した歩行」とケアプラン上に長期・短期目標としてあげながら、歩行・補助具の活用等の記録がまったくなく、転倒に配慮した記録が一切なかったり、またケアプランの長期・短期目標に「違和感なく食べるものの、今後、咀嚼しやすい献立」としながら、実際の実施記録には「食事の際のむせ込みが多く続く」というような、逆のことが記録化されているなど、矛盾する整合性のない記載がある記録を多く目にします。
言い換えると、転倒や誤嚥については、長期・短期目標にそれらの注意事項があげられていながら、実施記録の方では些細な表現のなかにプランや目標とまったく逆のことが記載されたような記録が目につくということです。「記録を読んで、どんなケアプランなのかが想像できるか?」、「ケアプランをみて、どんなアセスメントなのかが想像できるか?つまり、利用者像がイメージできるか?」といった逆の視点から、「限られた時間や交渉のなかで何を聞いておかなければいけないのか」「何をケアプラン上の目標としてあげるべきなのか」。そして「実際の介護サービスを提供していくうえで、現実可能なものであるのか」という視点を養っておくことで、裁判の勝敗はともかくとして、介護スタッフが実践している行為の正当性が裏づけられますから。
2005年1月 福祉リスクマネジメント研究所 所長 烏野 猛
介護事故が起きた場合に、介護にあたった職員個々の責任は問われるのでしょうか?
法人内で事故が起こった場合の責任の所在について、①職員に課せられる責任と、②法人に課せられる責任、とに分けて解説したいと思います。
まず、介護サービスを提供する場合、「誰と誰との契約なのか」という視点から考えてください。
当然、利用者本人と法人との契約ですね。場合によっては利用者ではなく、利用者の親族らを代理人として(法的な代理人ではない)署名・押印することも多々ありますが…。
ようするに、法人と契約をするということは(一度施設に置いてある契約書をご覧になってください)法人のトップつまり社会福祉法人である場合は理事長が利用者と契約を結ぶということになります。
しかし、利用者と理事長が契約を結んだとしても、直接理事長が食事介助や入浴介助をするわけじゃありませんよね。介護職員がそれら諸々の業務を日々こなすわけですよね。
つまり介護職員は、契約の当事者である理事長の代わりに利用者に対して介護サービスを提供するわけです。介護職員は、理事長からすると履行補助者という位置づけになり、履行補助者である介護職員の過失によって事故を招いた場合、利用者と介護職員との間には直接的な契約関係はないわけですから、介護職員個人が契約に基づく責任を問われることはありません。契約の当事者である法人トップの責任、つまり理事長の責任と言うことになります。
しかし、虐待など明らかに介護職員による過失で事故が起ったような場合には、介護職員に賠償責任が課せられ、さらに介護職員を監督する立場の法人のトップも使用者責任を問われることになります。
そしてこの介護職員とは、単に正社員(常勤)の職員という意味だけではなく、例えボランティアや実習生による無償の活動であったとしても、法人側には責任が求められます。その責任の程度は、正規の介護職員に課せられるほどの高い注意義務までは求められないにしても、「善良なる管理者の注意義務」(略称「善管注意義務」民法第400条)を負うとされています。
こうした施設内での介護事故に関しては、介助時また介助時以外(介助中ではなく、例えば利用者が一人で転倒したような、介護職員が関わっていない場合)、どちらにしても同じ責任が法人には求められます。
まず、介護サービスを提供する場合、「誰と誰との契約なのか」という視点から考えてください。
当然、利用者本人と法人との契約ですね。場合によっては利用者ではなく、利用者の親族らを代理人として(法的な代理人ではない)署名・押印することも多々ありますが…。
ようするに、法人と契約をするということは(一度施設に置いてある契約書をご覧になってください)法人のトップつまり社会福祉法人である場合は理事長が利用者と契約を結ぶということになります。
しかし、利用者と理事長が契約を結んだとしても、直接理事長が食事介助や入浴介助をするわけじゃありませんよね。介護職員がそれら諸々の業務を日々こなすわけですよね。
つまり介護職員は、契約の当事者である理事長の代わりに利用者に対して介護サービスを提供するわけです。介護職員は、理事長からすると履行補助者という位置づけになり、履行補助者である介護職員の過失によって事故を招いた場合、利用者と介護職員との間には直接的な契約関係はないわけですから、介護職員個人が契約に基づく責任を問われることはありません。契約の当事者である法人トップの責任、つまり理事長の責任と言うことになります。
しかし、虐待など明らかに介護職員による過失で事故が起ったような場合には、介護職員に賠償責任が課せられ、さらに介護職員を監督する立場の法人のトップも使用者責任を問われることになります。
そしてこの介護職員とは、単に正社員(常勤)の職員という意味だけではなく、例えボランティアや実習生による無償の活動であったとしても、法人側には責任が求められます。その責任の程度は、正規の介護職員に課せられるほどの高い注意義務までは求められないにしても、「善良なる管理者の注意義務」(略称「善管注意義務」民法第400条)を負うとされています。
こうした施設内での介護事故に関しては、介助時また介助時以外(介助中ではなく、例えば利用者が一人で転倒したような、介護職員が関わっていない場合)、どちらにしても同じ責任が法人には求められます。
2005年1月 福祉リスクマネジメント研究所 所長 烏野 猛
利用者さんが入所される前に、クレジットで何かを買い続けていたようです。クレジット会社(信販会社)から利用者ご本人に何度か連絡をしたようですが、施設入所になっているので連絡がとれず、利用者さんの親族に確認の電話が入ったようです。先日、親族の方がお見えになって、クレジットのローンを利用者さんである母親の年金から支払ったら、毎月の施設への利用料が払えない、という訴えがありました。 親族の方が言うには、「母親が認知症でボケている! ということが証明されれば、クレジットの方は支払わなくてもいいかも知れない」とおっしゃるのですが…。こんな場合、どうすればいいのでしょうか?
今後、このようなクレジットといいますか、ローン問題は多くなってくると思われます。
高齢者である利用者も、保護の対象としてだけではなく、商取引の当事者として購買者という位置づけが濃厚になってくるように思われますから。
さて、今回のご相談ですが、初期の認知症だったかも知れない高齢者(入所前の購入ということで)が、クレジットを利用して商品を購入した場合、何を買われたのか、というより「いくら程の商品」を買ったのか、という点がひっかかりますね。軽い認知症に罹患している高齢者は、外部の人からみると、ある部分ではしっかりとしているように見えるものです。健康器具(磁器マット入り布団など)や、高額な健康食品等を買ってしまうなどの被害が消費生活センターのまとめなどでも多くなっていると聞きます。
クレジットで商品を購入するとは、たとえば訪問販売員などが高齢者に商品を売り付けた場合、その商品代金を信販会社が販売者に購入者に代わって支払い、信販会社は購入者に対して与信調査をしたうえで金利を乗せて支払わせる、という流れをとります。
その際、販売員が購入者が高齢で判断能力の低下を利用して騙すように買わせたのであれば、明らかに違法性が疑われますし(ただし、立証が難しい)、また信販会社も電話等での与信調査の段階で、高齢者が高額な商品を購入しようとする場合には、それなりの注意が必要になります。
つまり法的には、販売会社および信販会社が過量販売ないし過剰与信をおこなったとみなされ、公序良俗に反し契約そのものが無効になる可能性が非常に高いということです。
ですから、親族の方が「認知症であることが証明できれば、クレジットの残金を支払わなくてもいいかも…」と言ったことに対してはその通りなのですが、先にも触れましたように、その立証が非常に難しいので、そう簡単にはいかないように思われます。
その余波を受けて、今度は利用料が支払えない、というのは頭を抱える問題ですよね。「このような問題は家族間で解決して下さい」と言いたいところですが、利用料を滞納し始めれば、法人としても事情を聴く必要が生じますし、問題解決に向けての助言も家族側からは求められるでしょうから…。
先程の話に戻りますが、クレジット会社や信販会社には、一般論として顧客の年齢や職業、収入や資産状況、顧客の生活状況および顧客とのこれまでの取引状況等を考え合わせ、顧客に対する不当な過量販売その他適合性の原則から著しく逸脱した取引をしてはならないとされていますし、また不当に過大な与信をしてはならない信義則上の原則を負っています。
ですが、割賦販売法38条は割賦購入斡旋業者に対して、過剰与信防止義務が認められる前提となる法制度が未だ整備されていない状況ですし、店舗内における過剰売買に関する規制も十分ではないという限界もあります。一般の商取引においても限界を抱える問題が、施設に持ち込まれるとは、これまでの高齢者施設の中ではあまり想定されていなかったケースですね。
高齢者である利用者も、保護の対象としてだけではなく、商取引の当事者として購買者という位置づけが濃厚になってくるように思われますから。
さて、今回のご相談ですが、初期の認知症だったかも知れない高齢者(入所前の購入ということで)が、クレジットを利用して商品を購入した場合、何を買われたのか、というより「いくら程の商品」を買ったのか、という点がひっかかりますね。軽い認知症に罹患している高齢者は、外部の人からみると、ある部分ではしっかりとしているように見えるものです。健康器具(磁器マット入り布団など)や、高額な健康食品等を買ってしまうなどの被害が消費生活センターのまとめなどでも多くなっていると聞きます。
クレジットで商品を購入するとは、たとえば訪問販売員などが高齢者に商品を売り付けた場合、その商品代金を信販会社が販売者に購入者に代わって支払い、信販会社は購入者に対して与信調査をしたうえで金利を乗せて支払わせる、という流れをとります。
その際、販売員が購入者が高齢で判断能力の低下を利用して騙すように買わせたのであれば、明らかに違法性が疑われますし(ただし、立証が難しい)、また信販会社も電話等での与信調査の段階で、高齢者が高額な商品を購入しようとする場合には、それなりの注意が必要になります。
つまり法的には、販売会社および信販会社が過量販売ないし過剰与信をおこなったとみなされ、公序良俗に反し契約そのものが無効になる可能性が非常に高いということです。
ですから、親族の方が「認知症であることが証明できれば、クレジットの残金を支払わなくてもいいかも…」と言ったことに対してはその通りなのですが、先にも触れましたように、その立証が非常に難しいので、そう簡単にはいかないように思われます。
その余波を受けて、今度は利用料が支払えない、というのは頭を抱える問題ですよね。「このような問題は家族間で解決して下さい」と言いたいところですが、利用料を滞納し始めれば、法人としても事情を聴く必要が生じますし、問題解決に向けての助言も家族側からは求められるでしょうから…。
先程の話に戻りますが、クレジット会社や信販会社には、一般論として顧客の年齢や職業、収入や資産状況、顧客の生活状況および顧客とのこれまでの取引状況等を考え合わせ、顧客に対する不当な過量販売その他適合性の原則から著しく逸脱した取引をしてはならないとされていますし、また不当に過大な与信をしてはならない信義則上の原則を負っています。
ですが、割賦販売法38条は割賦購入斡旋業者に対して、過剰与信防止義務が認められる前提となる法制度が未だ整備されていない状況ですし、店舗内における過剰売買に関する規制も十分ではないという限界もあります。一般の商取引においても限界を抱える問題が、施設に持ち込まれるとは、これまでの高齢者施設の中ではあまり想定されていなかったケースですね。
2005年1月 福祉リスクマネジメント研究所 所長 烏野 猛
今の利用契約書には利用料を滞納した場合の規定がありません。現在利用料金を滞納している方への対応と、今後、利用者さんからの利用料の滞納があった場合にはどうすればいいでしょうか?
このような問題は、今後ますます増えてくると思われますね。
まず、「サービス利用契約書」や「重要説明書」等に利用者さんが支払うべき支払い義務の規定がなくても、法人が介護サービスを提供している以上、利用者さんが法人に対して利用料金の支払義務があるのは当然のことです。
おそらく、身元保証人の方や、身元引受人の方が当人の介護サービス利用の際の契約書に名前が載せられていると思いますが、その保証人の方や引受人の方に当人の未納分利用料金を支払ってもらう手もありますが、彼らに利用料金を立て替えて支払う法的義務まではありません(彼らが善意で支払ってくれれば良いのですが…)。
なので、法人側としては、保証人や引受人に事情を説明して当事者に代わって支払ってもらえるかどうかをお願いすることまではできますが、法人側に請求するだけの権利があるかといえば、NOです。
手続き的に言えば、入所施設であれば施設からの退去を求め、民事上、未払い分の利用料金を強制的に取り立てることは法的には可能です。実情としても待機の高齢者が非常に多く存在する中、きちんと支払ってもらえるであろう利用者さんを確保することは、法人経営として当然のことですから。
しかし、そうした場合の裁判費用や時間的手続き的な手間の問題だけではなく、物理的に強制執行することは法的にはできるものの現実問題としては難しいでしょうね。
現在のところ法人側としてとれるリスクヘッジとしては、成年後見制度の利用しかないと思われますが、利用料金滞納の事実経緯が、ご本人の年金等の資力が枯渇したのか、親族等に年金通帳を含めた金銭管理を依頼していたにもかかわらず、当の親族が使い込んでしまい利用料金が支払えないのか、等の確認が急がれます。
また、たとえ適切な後見人が見つかりそうな場合であったとしても、実際の成年後見制度の利用については、管理費と言いますか手数料といいますか、月に数万円程度かかることが予想されますので、資産の乏しい高齢者には現実的に利用できる制度ではないかもしれません。
ご質問の答えになりますが、現在もう既に滞納している利用者さんの場合には、上記の理由から、今のところ打つ手がない様に思われます(生活保護という手続きの方法もないわけではありませんが…)。
そして現在、滞納についての利用料金徴収の記載が「契約書」「重要事項説明書」になく、今後、滞納する利用者さんが現れるリスクを回避するには、早急に利用料金についての規定を契約書上明記し、かつ親族等に対して利用料金が滞った場合に代わりに支払ってもらえるような拘束力のある文章を交わしておくことをお勧めします。
まず、「サービス利用契約書」や「重要説明書」等に利用者さんが支払うべき支払い義務の規定がなくても、法人が介護サービスを提供している以上、利用者さんが法人に対して利用料金の支払義務があるのは当然のことです。
おそらく、身元保証人の方や、身元引受人の方が当人の介護サービス利用の際の契約書に名前が載せられていると思いますが、その保証人の方や引受人の方に当人の未納分利用料金を支払ってもらう手もありますが、彼らに利用料金を立て替えて支払う法的義務まではありません(彼らが善意で支払ってくれれば良いのですが…)。
なので、法人側としては、保証人や引受人に事情を説明して当事者に代わって支払ってもらえるかどうかをお願いすることまではできますが、法人側に請求するだけの権利があるかといえば、NOです。
手続き的に言えば、入所施設であれば施設からの退去を求め、民事上、未払い分の利用料金を強制的に取り立てることは法的には可能です。実情としても待機の高齢者が非常に多く存在する中、きちんと支払ってもらえるであろう利用者さんを確保することは、法人経営として当然のことですから。
しかし、そうした場合の裁判費用や時間的手続き的な手間の問題だけではなく、物理的に強制執行することは法的にはできるものの現実問題としては難しいでしょうね。
現在のところ法人側としてとれるリスクヘッジとしては、成年後見制度の利用しかないと思われますが、利用料金滞納の事実経緯が、ご本人の年金等の資力が枯渇したのか、親族等に年金通帳を含めた金銭管理を依頼していたにもかかわらず、当の親族が使い込んでしまい利用料金が支払えないのか、等の確認が急がれます。
また、たとえ適切な後見人が見つかりそうな場合であったとしても、実際の成年後見制度の利用については、管理費と言いますか手数料といいますか、月に数万円程度かかることが予想されますので、資産の乏しい高齢者には現実的に利用できる制度ではないかもしれません。
ご質問の答えになりますが、現在もう既に滞納している利用者さんの場合には、上記の理由から、今のところ打つ手がない様に思われます(生活保護という手続きの方法もないわけではありませんが…)。
そして現在、滞納についての利用料金徴収の記載が「契約書」「重要事項説明書」になく、今後、滞納する利用者さんが現れるリスクを回避するには、早急に利用料金についての規定を契約書上明記し、かつ親族等に対して利用料金が滞った場合に代わりに支払ってもらえるような拘束力のある文章を交わしておくことをお勧めします。
2005年1月 福祉リスクマネジメント研究所 所長 烏野 猛
土地や山などの不動産を多く所有していた利用者さんが亡くなりました。介護事故での死亡ではありません。死亡そのものについては親族間での争いはないのですが、遺言書が2通出てきて、1通は「全財産長男に」というもの。2通目は「全財産次男に」という内容です。当然、認知症状があったので、遺言を書いた時に認知症があったのかどうかという点で、長男からは「介護記録を見せろ」という訴えがあり、次男からは、「長男から介護記録を見せろ、と言われても絶対に見せないでくれ」と言って来られました。どうすればいいでしょうか?
大変難しい問題ですね。まず、遺言については、何通書いても良いことになっています。
通常、直近に書いた遺言書が有効になるのですが、認知症状のある利用者さんの場合の遺言書については、遺言内容作成時において、意思能力・判断能力の有無が争点になります。認知症があれば遺言書を書くことができないという意味ではありません。
遺言に求められる能力は、高度な判断能力が求められるわけではなく、それよりも若干低い能力である意思能力程度でよいとされています。ですから、遺言ができる能力は、未成年でありながらも15歳以上と、民法でもゆるい規定になっています。
次に、認知症の方には遺言能力がない、つまり書いた遺言書はすべて無効になるのか、という点です。認知症であっても、「本心に復している」状況にある場合には有効です。その「本心に復しているか否か」の判断に、介護記録が非常に重要になってきます。
最後に、介護記録をどの親族の範囲にまで開示することができるのか? とくに、今回のように親族間で全く逆の対応を法人に求めてきた場合、どうすればいいのでしょうか?
介護の領域では、介護記録の開示や開示範囲について、いまだ十分に論議がなされていないように思いますが、医療領域ではインフォームドコンセントの流れを受けて、記録の開示・開示範囲について学会でもガイドラインが出されています。それによると、「該当する本人と最も交渉の程度が密な者」の意見が重視されるものとなっています。 今回の質問のケースで言えば、遺産という親族間の争いに法人が巻き込まれてしまったという構図ですが、死亡した利用者と長男・次男との交渉程度を法人が判断し、その選択結果を長男・次男にも通知するところまでしか、法人としての役割はないと思われます。その結果、長男・次男どちらかが法人に対して異議を申し立ててきたとしても、法人側に違法性はありません。
通常、直近に書いた遺言書が有効になるのですが、認知症状のある利用者さんの場合の遺言書については、遺言内容作成時において、意思能力・判断能力の有無が争点になります。認知症があれば遺言書を書くことができないという意味ではありません。
遺言に求められる能力は、高度な判断能力が求められるわけではなく、それよりも若干低い能力である意思能力程度でよいとされています。ですから、遺言ができる能力は、未成年でありながらも15歳以上と、民法でもゆるい規定になっています。
次に、認知症の方には遺言能力がない、つまり書いた遺言書はすべて無効になるのか、という点です。認知症であっても、「本心に復している」状況にある場合には有効です。その「本心に復しているか否か」の判断に、介護記録が非常に重要になってきます。
最後に、介護記録をどの親族の範囲にまで開示することができるのか? とくに、今回のように親族間で全く逆の対応を法人に求めてきた場合、どうすればいいのでしょうか?
介護の領域では、介護記録の開示や開示範囲について、いまだ十分に論議がなされていないように思いますが、医療領域ではインフォームドコンセントの流れを受けて、記録の開示・開示範囲について学会でもガイドラインが出されています。それによると、「該当する本人と最も交渉の程度が密な者」の意見が重視されるものとなっています。 今回の質問のケースで言えば、遺産という親族間の争いに法人が巻き込まれてしまったという構図ですが、死亡した利用者と長男・次男との交渉程度を法人が判断し、その選択結果を長男・次男にも通知するところまでしか、法人としての役割はないと思われます。その結果、長男・次男どちらかが法人に対して異議を申し立ててきたとしても、法人側に違法性はありません。
2005年1月 福祉リスクマネジメント研究所 所長 烏野 猛